今回は、前回の記事で書ききれなかった奏法について記述していきます♪
テーマは【ストローク】!!
今回は基本的な考え方を説明する回なので、2本マレットを想定しています♪
大きく分けてストロークには2種類あります。
それが
【アップストローク】と【ダウンストローク】
です。
何となくどういうことか想像できる人もいるんじゃないかなと思うのですが、
これ、【アップストローク】が上に向かって力を逃す奏法
【ダウンストローク】は下に力を伝達するような奏法
と僕は分類しています。
この2つの奏法のニュアンスが違うところなんかを説明していきたいと思います。
ストロークを変えることによるメリット
これがなければ、ストロークを変える意味なんかないじゃん!!
と言われちゃいますもんね。
当然あります。
前回の記事でも少し触れた部分と重複してくるのですが、
マリンバは、高音と低音では音盤の厚みが違います。
また振動の仕方も鍵盤(音程)の高さによって大きく変わってくるので、
マレットを使い分けよう!!
なんてお話をしました。
ベースラインを演奏するためのベースマレットは重みがあるので、上に力を逃すことが難しいんです。よって、低い音域は基本的には
【ダウンストローク】が奏法としてはベスト。
そしてこれは、厚みがなく、響きとして支えなければならない低音域の発音とも相性がいいのです♪
このことによって、それぞれの鍵盤(主に低音域)に不必要な力が入ったり、鍵盤を破壊したりすることを防止していきます。
そして比較的軽いマレットで演奏する高い音域は、
【アップストローク】で演奏する。
高音域の鍵盤は厚みがあるおかげで、鍵盤に対して過度な力が入るということはあまり想定されません。
よって高い音を歯切れよく演奏するために、響かせるというよりも
「しっかり発音してあげる」
ことが大事になってきます。
マリンバを演奏する際に、「押さえつけないこと」は当然大切なことなのですが、第二段階として、弾いた力を【逃して響きに変換する】ということもなお大切です。
アップストローク
先ほども記述したように、高音域は鈍い当たりで演奏しても音が遠くへ飛んで行きません。
しかも厚みがある分、芯の音を出してあげようとすると、インパクトをかなりしっかり出してあげなければならない。
その時に思いっきり叩いただけでは、力は鍵盤の表面を伝導するだけで、芯には届きません。
よってインパクトした瞬間に手首を返して、引く力(弾くではなく)によって力の逃げ道を作ってあげることが重要になってきます。
感覚としては、【ムチ】のようなイメージ。
皆さんも経験があるんじゃないかなと思うのですが、昔、タオルを使って遊びませんでした?
軽く前にタオルを投げ出して思いっきり引っ張ってみると、タオルに力が伝わって「パチン」と空気を叩く音がする
ってやつです。
やったことがない人は感覚を掴(つか)むために是非、トライしてみてくださいね♪(人に当てないように)
手首の動かし方にも注目するとベターです♪
これを鍵盤上で体現しようとすると、力の「抜ける方向が上を向く」ため、
アップストロークになります。
何となく直訳すると、「上方向の打撃」となってしまって、本質的な意味を捕らえづらくなるので、原理を理解した上で、感覚をつかんでいきましょう。
冒頭で【アップストローク】を力を上に逃すと表現したのはこのためです♪
ダウンストローク
アップストロークに比べると、やや後から覚えることになるでしょう。
が、実はトレモロに重みをつけて演奏したりする時に、知らず知らずのうちに習得しているかもしれないテクニックなのですが、自覚があまりないかもしれません。
こちらは、主に低音部(真ん中の「ド」よりも低い音域)で使われることが多い奏法です♪
マレットや腕の重みを、鍵盤よりも下のパイプを狙って打ち下ろしていく感覚で、
ハンマーで打つのようなイメージ。
でこの時に逃す力の方向は【横】です。
なぜかというと、下に力を逃がそうにも現実的にそこには鍵盤があって、力を下に逃すことができないからなんです。
アップストロークの場合には、上に障害物はないですからねw
インパクトの瞬間に生まれた力をしっかり受け流さなければならないので、ダウンストロークの場合には、横に向かって力を逃すことをオススメします。
アンサンブルにおけるベースパートや楽曲の中で低音域が多用されるシーンなんかでは大活躍します。
目指すべき音は、余韻が長くなり続ける音です。
低音部の音は、過度な力が入ると振動が止まってしまうので、力を入れるというよりも、しっかり腕の重みを利用してあげつつ、重力に逆らわないような体の使い方をしてあげるということですね。
ここが説明するのが難しいところですが、目指す音を明確に思い描くことによって、トライ&エラーを繰り返しながら、理想の音作りをしていきましょう♪
まとめ
今回はヘビーな内容なので、いつもより短めにしておきます♪
ストロークを変えることによって、使用するテクニックは変わるのですが、
基本的なことは何一つ変わりません。
準備をする→演奏する→弾き終わりの処理が変わるだけですが、
音色には大きく影響が出ます。
しかも準備をしっかりしないと発音が悪くなることもしばしばあるので、
出したい音をイメージしてから、演奏のための準備に入る
というルーティーンを確立していくことこそが、今回の最も重要なポイントになるわけです。
準備動作における時間の使い方に無駄がなくなると、演奏中の動作で止まっている時間が激減します。
ひいてはこれこそが「滑らかな演奏」に繋がっていくので、一緒に研究していきましょう♪
では、また次回♪
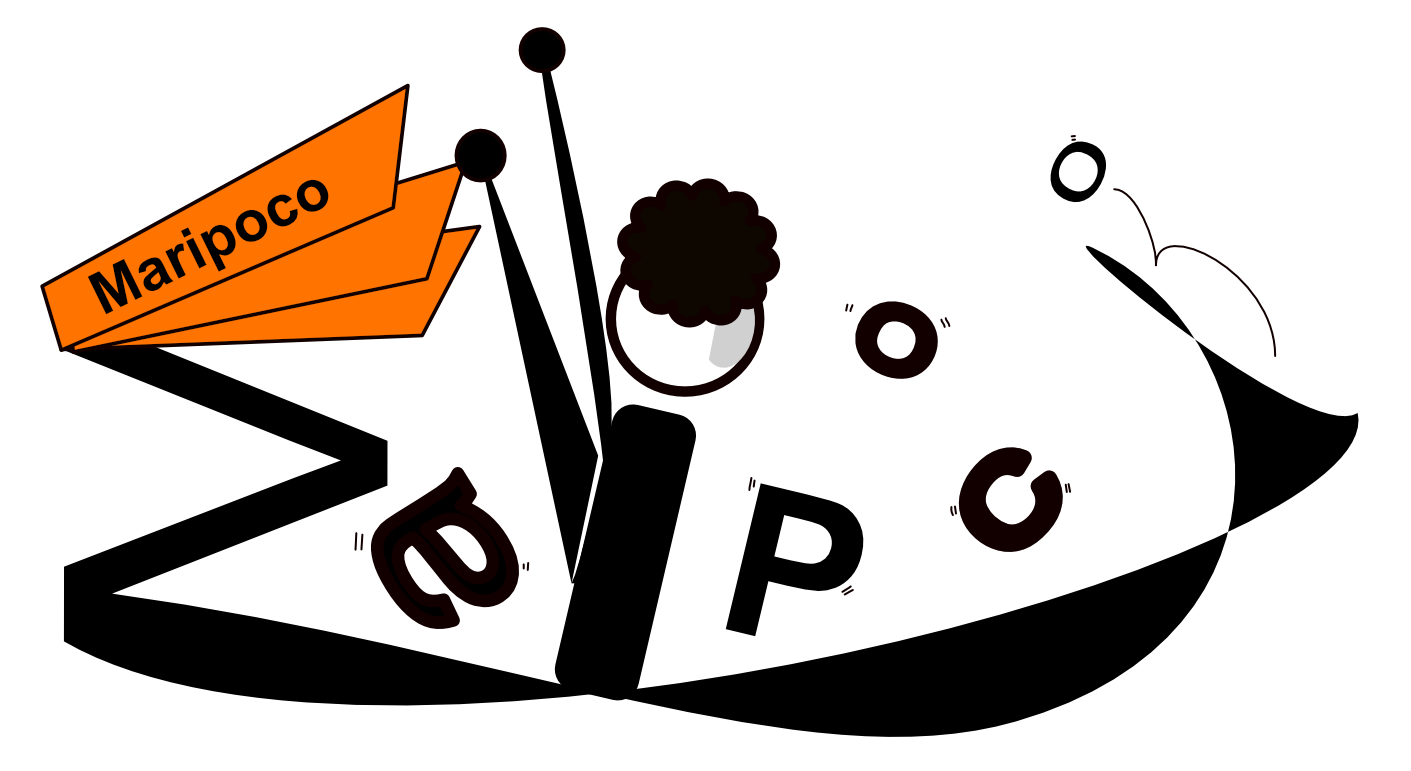



コメント