こんにちは!
前回、基本中の基本、マレットの持ち方・構えや立ち位置について
の中でお話ししましたが、
今回からは実際に楽器を弾いてみよう!!
というシリーズです。
- 楽器がご自宅にある
- 何かつまづいていることがある
- 昔習ったんだけど、今は曖昧になりつつある
こんな方達におススメの記事です。
演奏の動作
マリンバの演奏者や打楽器奏者の実際の演奏を見たことがある、または
習っている方、実際に演奏したことがある方はご存知のことでしょうが、
マリンバは打楽器です。ドレミがあるので音階打楽器ですね。
(僕はあまりこの表現は好きではないですが)
マリンバは打つとか叩く動作として理解していただいた方が、
話が早そうなので、弾くとは言わずに説明していきましょう。
自分の体のこと
まずこれ。
何か楽器を始める時に考えていただきたいのが、自分の体のことをよく知ること。
とても重要です。
マリンバを演奏する際には、立奏が基本です。
(知り合いに座って演奏する人がいますが、彼以外に座奏者を知りません。)
立奏する時点で体の使い方が大切だな、と感じた方はいいアンテナをお持ちですね。
左右どちらかに体重が偏っていたり、膝が伸びきっていたりすると、
マリンバの横幅(広いですからね。)に対応できなくなります。
演奏する前に準備運動も忘れないように。(手首足首でおなじみのアレは絶対)
移動術についてもマリンバを演奏する上で、重要なウエイトを締めることになるので、別の回でもフォーカスしていきますが、
今回は腕の説明からいきましょう。
腕の関節
腕の関節の中でもまずは、
- 手首
- 肘
- 肩
この3つはマリンバを演奏する上でとても重要な働きをする部分です。
何の先入観もなく見よう見まねで叩く動作をしようと思った時、
無意識にこの関節が動くはず。
これを意識した上でマリンバをスタートできるか否か、これがとても重要なのです。
まず、エクササイズとして各関節を使ったものを紹介していきます。
エクササイズ1
真ん中の「ド」を片手づつ叩く練習をしていきます。
まずはおへその位置を「ド」の目の前に持ってきて
右手から(逆の手はおろしておきましょう)
- シェイクハンズのフォームでマリンバの前にマレットを構えたら肘の高さ・手首の高さを変えないように手首を上に返します。(この時に力が入る)手首から先が動いているイメージ
- →リリース(重力と手の重さを利用して開放する)して鍵盤に当てる。(うらめしやのポーズ)
- これの繰り返し
左右の手で数回鳴らしてみたら「脱力の感覚」を養っていってください。
※注意ポイント
- 構えた時に肩が上がっていないことを確認する
- 肘が開きすぎていないことを確認する
- 手首が鍵盤の高さから見て高くなりすぎていないか確認する
- 「叩こう」と考えると重力を感じずらくなるので、「脱力する」と考える
エクササイズ2
今度は肘の高さを固定して肘から先を動かして
エクササイズ1と同じことをしていきます。
ターゲットは真ん中の「ド」。
- 握っている手を肩に近づけるようなイメージで持ち上げる(力こぶの筋肉を使っています:上腕二頭筋)
- リリースする→繰り返し
1の時とは違い腕の重みが足されるので音量が大きくなりますね!
動作とは表裏一体の2つ以上の動きを1つにしたもの
上記のエクササイズをやってみていただいた方には、
どんな感じか掴めたかと思いますが、叩く動作って1つではありません。
僕たちが日常生活の中であまりに体がよく動いてくれるので、
普段考えもしないことなのですが、何か新しく始める時に
フォームを体得するのに時間がかかってしまうのは、
実はこんな体の動かし方だとか、感覚が伴わないからなんです。
では、打つ・叩くのにはどんな動きが含まれるでしょうか?
準備
これが手首を上に返す力だったり、肘から先を持ち上げる力だったりします。
マリンバの演奏をする中で、この動きを準備の動作と言います。
で、この準備の動作は必ず重力に逆らいます。
※重力ってなあに?ってなったお友達は両腕を前に伸ばして5時間我慢できるかやってみてね!(嘘だよ!やらないでね)
打つ・叩く
準備なしにできないのがこの打つ・叩くという動きです。
腕を持ち上げないでこの行為はできませんからね。
で、なぜこの打つ・叩くという表現を僕がしたくないかというと、
「この言葉が先入観を与えるから」なんです。
この動きには、重力や腕の重さを利用するという意味が含まれていないように感じてしまうからなんです。
先ほどのエクササイズの中にもリリース(開放する)という言葉を使いましたが、感覚的にはこれです。
「準備をする時に入れた力を抜いてあげること」が大事です。
今日のキモ・脱力
この「脱力」。演奏だけではなく、様々な分野で大事だと呼ばれるこの奥義的なもの、
演奏ができるようになってしまってから、この脱力を体得することは大変難しいです。
かくいう僕も、大学卒業をしてからフォームの大改修をするという苦行をしました。
読んで字の如く、力を抜くという意味には違いないのですが、
ただ単に力を抜いてしまったら演奏はできません。
余分な力を抜くということなんです。
もっと言うと、余分な力を何か別の力で代替できないか考えて力に頼らないこと
と意訳するべきだと僕は思います。
さあ、次回はもっと具体的に音を出していきます。
乞うご期待!
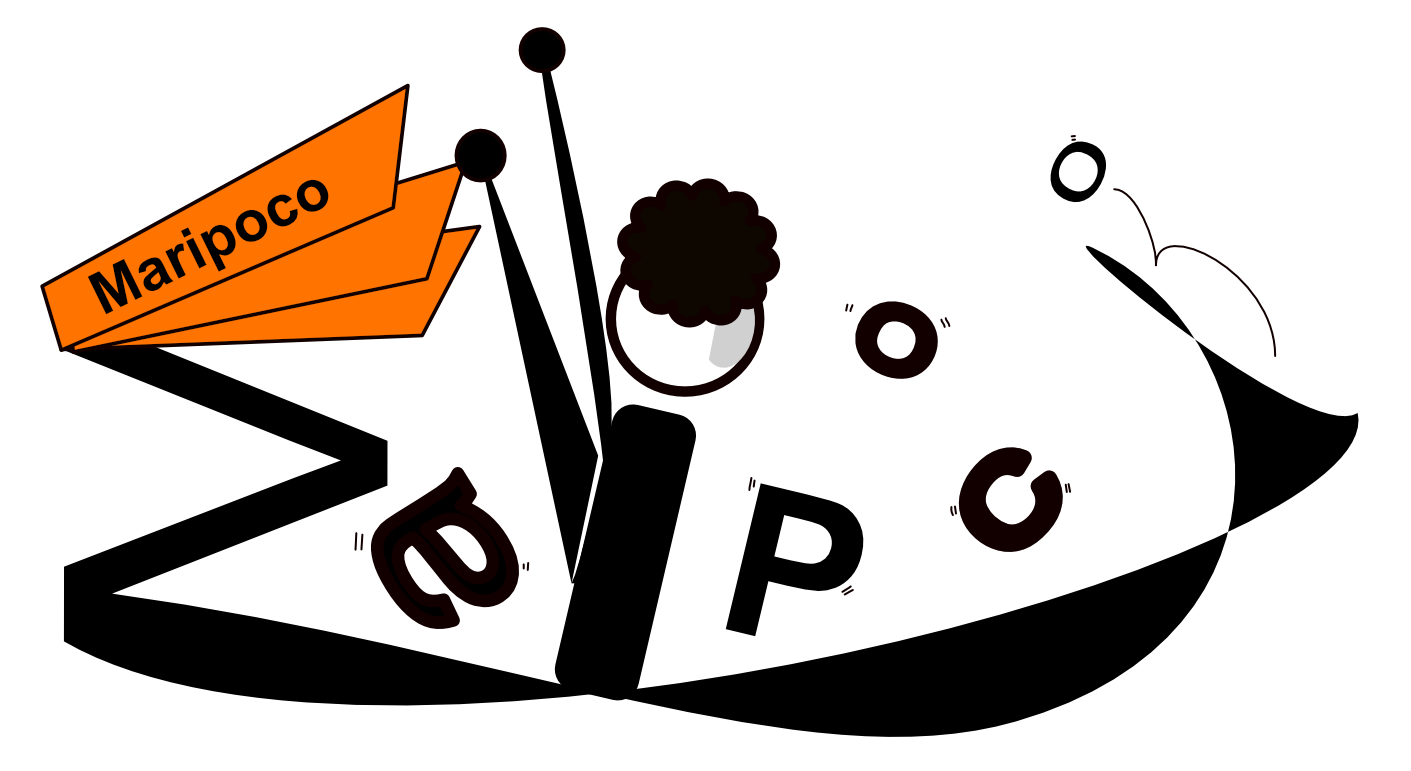



コメント